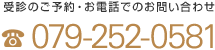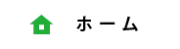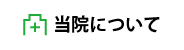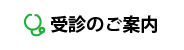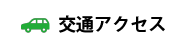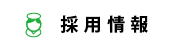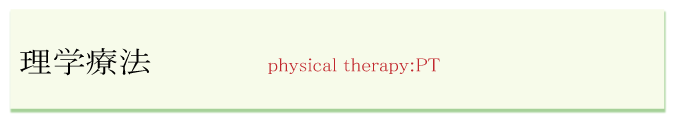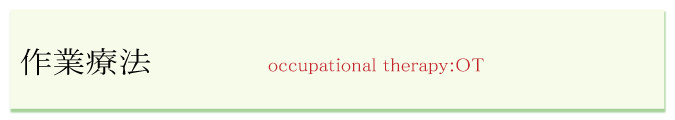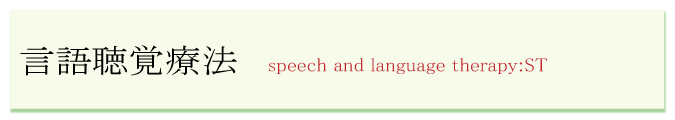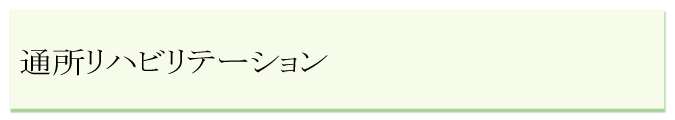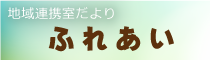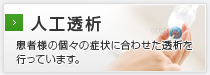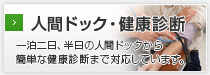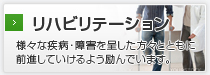リハビリテーション科
リハビリテーション(rehabilitation)とはre「再び」、habilitation「適合した、ふさわしい」という意味があります。リハビリを行うことで機能回復のみではなく、その方らしい生活を取り戻し、地域社会へ復帰していくことが大切あると考えています。
当科では、「癒しのある空間づくり」「気持のわかるセラピストへ」「チームアプローチ」を胸に、患者様の日常生活をより良いものにする為、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の各セラピストが専門性を生かし個別治療を行っています。また、治療に関わる多職種との定期的な回診やカンファレンスを行い、連携を図ることでスタッフ一丸となって患者様のニーズにお応えできるよう努力しています。
そして、多職種と連携してポジショニングやリハ栄養に取り組み、患者様の安楽な姿勢の確保や褥瘡(床ずれ)予防、必要な方にはリハタイムゼリーを提供し、サルコペニアやフレイルの予防に取り組んでいます。
リハビリテーション科概要
スタッフ
専任医師:1名 理学療法士:12名 作業療法士:5名 言語聴覚士:3名
アシスタント:常勤3名、非常勤1名
占有面積
運動療法室(理学療法、作業療法):226.15㎡、言語聴覚室:27.54㎡(内法)


承認施設基準
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ、運動器リハビリテーション料Ⅰ、
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
診療時間
| 外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | 13:30-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 13:30-14:30 |
入院診療は、日曜日・年始を除く、9:00-18:00までとなります。
リハビリテーション お問合せ
079-252-0581(代)
姫路第一病院 リハビリテーション科
お気軽にお問合せください